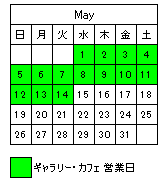<2013年3月号>
<2013年3月号>

家族の固い絆から生まれる須田帆布のバッグ
いまや、全国的に人気の“須田帆布”。
茨城県・つくばに、しっかり根を張るこの店には、次から次へとお客様が訪れます。
全く素人の須田栄一さんが、帆布を使ってバッグを作り始められたのが1986年。
それからずっと多くの方に支持され続けています。
その頃と大きく変わったこと。
それは、御嬢さんの雅代さんがカナダ留学時に知り合った靴職人のコーラムさんと結婚し、
彼が須田帆布のバッグづくりに加わったこと。
ストイックにきちんとした仕事をしなければ気が済まない完璧主義のコーラムさんと
自己流で情熱的にバッグづくりに没頭する須田栄一さん。
この二人の激しいバトルと和解を何度も繰り返し、“須田帆布”ブランドがより確立してきました。
普通、日本人のお婿さん、あるいはお弟子さんなら、ボスである栄一さんに口ごたえしたり批判したりということはしないでしょう。
カナダ人のコーラムさんは、率直な自分の意見を躊躇なく訴えます。
それも、須田ブランドのバッグづくりを誰よりも真剣によいものにしようという情熱があってのこと。
熱い二人の格闘は、互いの信頼に代わり、よりよいモノづくりに邁進する心強い“同志”であり“同士”となったのです。
栄一さん・コーラムさんがバッグづくり、雅代さんが営業、栄一さんの奥様・喜美枝さんが経理やお孫さんの世話。
須田ファミリーが一体となり、固い絆で結ばれ、それはバッグづくりのみならず、家庭の幸せな空気をもたらしています。
週に一度は、以前買われた方からのお修理の依頼がくるそうです。
体の一部となったような使い込まれた須田さんのバッグを、修理してまた永く持ち続ける。そんな愛着の湧くようなバッグなのです。
2年前に須田さんの展覧会をし、その時にバッグを買われた方たちが、「またやらないの?」というリクエストの声が多いのも事実です。
須田ファミリーの真摯な姿勢と熱くて温かい精神が、使う人にも伝わるものづくりと言えるでしょう。
tiny knotsのギャッベ

イラン南西部ファルス地方で生活をする遊牧民族(主にカシュガイ族)が織っている原始的な製法の比較的目が粗く毛足の長い絨毯。
これが“ギャッベ”です。
ギャッベは、ペルシャ絨毯のような装飾品というよりは遊牧生活の中、テント内の地面に敷くための大切な生活用品。
冬の氷点下の寒さや夏の40度を超える暑さをしのぐため、また地面の硬さを和らげるためにギャッベの持つ耐久性・クッション性が必要。
材料となる羊毛は平地に住む羊よりも耐寒性に富み、脂質を多く含むため、汚れにくく丈夫です。
ギャッベはその工程、つまり毛梳き・紡ぎ・染め・織りのほとんどを彼らの手で行います。
織り柄が民族や家庭ごとに違うのですが、そのデザイン上とても重要な染めは、
身の回りにある植物で染められ、天然の染料を使うことで虫やサソリから守る役割も果たします。
織りについても、木や鉄の棒を組み合わせた簡単な道具に糸を巻きつけたものに、
地道に毛糸を結んでは切るという作業を繰り返し地面に水平に織っていきます。
以前、イラン人の実演を見学したことがありますが、長時間で少しだけしか織り進めない気の長い作業です。
長い間、遊牧民が自分たちの移住生活用品として作っていたものですが、20世紀半ばにヨーロッパの絨毯コレクターが紹介したことから脚光を浴びることになりました。
以来ギャッベは欧米中心に広まりましたが、彼らの靴履きの生活に元来の毛足の長いギャッベはなじまず、
次第に毛足が短く織り目も細かい洗練されたデザインの物が制作されるようになりました。
一方で、ギャッベが日本に紹介されたのはそれほど前のことではないようです。
遊牧民は厳しい外気から守られたテント内で、日本人と同じように靴を脱いでくつろぐ柔らかいギャッベの感触は彼らの生活に温もりをもたらします。
同じ床座の文化を持つ日本で“古くて新しい”生活道具として、しっかりとした厚みとフカフカの手触りのギャッベが親しみ深く楽しむことができるにちがいありません。
今回お世話になるtiny knotsでは、代表・神戸智恵子さんの知人であるイラン人の安藤ラミン氏が直接現地のテントを訪ねて買い受けてきた上質のものを、
リーズナブルに提供してくださいます。ぜひ暮らしの中で、ギャッベの気持ちよさを体感してください。

長嶋貴子さんのガラス絵
長嶋貴子さんは、多摩美術大学の立体デザイン科ガラスコースのあと、富山ガラス造形研究所、金沢卯辰山工芸工房と長年ガラスを学びました。
ガラス素材の溶けた時の色・形、膨らむ時の柔らかい質感に魅力を感じて大学に入られたのですが、
学生時代、絵を描くことがおもしろくなって、両方を組み合わせた今の作品に至ったそうです。
絵を描くといっても、ガラスに絵付けをすることはとても手間がかかります。
吹きガラスの炉の高温で焼きつくエナメル原料で、宙吹きの皿にペイントしたものを、600度くらいの電気炉の中であたためる。
溶かしたガラス片を付けた竿にその皿を圧着させ取り出し、吹きガラスの炉に出し入れして少しカタチを整えながら
炉の約1200度の熱で絵を焼き付けます。
長嶋さんの作品を初めて見たのは、5年ほど前に卯辰山工房の見学に行き、そのロビーのショーケースの中の卒業生作品のうちのひとつ。
ポップでシュールでおもしろい絵つけのグラスでしたが、その時は時間がなく素通りしてしまいました。
千葉に帰ってからしばらく気になっており、その事務所に問い合わせて長嶋さんにメールをしましたが、アドレスが違ったのか連絡とれず。
その後何年か経った昨年の夏、陶芸家の戸出雅彦さんの展覧会の際、以前、卯辰山の講師だった彼から連絡先を知ることとなりました。
ギャラリーの仕事をしていると、いろんな人との出会いと繋がりに恵まれ、ひょんなことから新たな縁が生まれます。
今回は、ユーモアあふれる絵付けの皿(これは壁にも掛けられる仕掛けもあり)やグラスや花器などを展開いたします。
長嶋さんは、その絵からストーリーを想像しながら暮らしの中で楽しく使ってほしいとおっしゃっています。
どうぞお楽しみに。
コラム vol.52 "家族の固い絆から生まれる須田帆布のバッグ" "tiny knotsのギャッベ" "長嶋貴子さんのガラス絵"