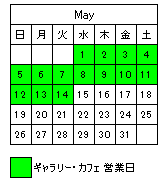<2016年2月号>
<2016年2月号>
関昌生さんの柔軟な発想力
福岡うきは市“四月の魚”を営むお店のかたすみで、いつも関さんはデスクの前に座ってペンチを片手にワイヤーを器用に曲げたり伸ばしたりしておられます。
シンプルな線でできる美しくもモダンな関さんの作品。
当初から特にこれを作りたいというものがあるわけではなく、手が動くのに任せて自由に作っているそうです。
ご本人は、お店の運営も作家活動も年齢とともにムリをせず、できそうなことをただやるだけだと謙虚におっしゃいますが、、
関さんの作品は見るたびに新鮮でユニークで感性豊かなのに感心します。
そしてそのバリエーションの多さにも驚きます。
柔軟な発想によって、肩肘張らないユルいイメージのものにも、幾何学的で何かの細胞模型のようなビシっとしたものにも神経がいきとどいています。
一本の何の変哲もないまっすぐな鉄線が関さんの魔法の手にかかると、風通しのよい立体になり、そこに温度が生じる。
その周囲に異なる空気のようなオーラのようなものが現れ、新たな“場”ができるような気がします。
関さんの展覧会はもう何度めかですが、ファンの方にも初めて見る方にも、フッと微笑ませて心をとらえられる魅力にあふれています。
今回も会期が始まるギリギリまで制作されるとのこと、どんな楽しいラインナップが登場するか待ち遠しいです。
ぜひご高覧くださいませ。
落合芝地さんの拭き漆
京都で生まれ育ち、現在、滋賀で漆器の制作をする落合芝地さん。
お母様が美術や洋裁がお好きで、落合さんの幼い頃から身の回りに手作りのものがたくさんあったそうです。
京都市の伝統工芸育成事業で漆、特に蒔絵を学びましたが、きらびやかな蒔絵ではなく実用的なものを作りたいと思いました。
木地の発祥の滋賀・永源寺で木工ろくろの基礎を学びました。
誰かの弟子になることなく独立。自宅のはなれに作られたアトリエで、木地を挽き、漆を塗り、多くの制作工程をコツコツと進めていきます。
庭では子供たちが遊び、いつも暮らしの中に家族と仕事があるというこの状況が気に入っているとのこと。
樹種によってそれぞれの特徴があり、その表情や木目を最大限に生かしたいと強調されます。
漆の塗りの技法はいろいろありますが、落合さんは最近“拭き漆”を主に制作しています。
何重にも塗り重ねられた漆器は、その下の木地の肌が全く見えませんが、漆を塗っては拭き塗っては拭きを繰り返すこの技法だと下が見えます。
オイルフィニッシュとは趣が異なる拭き漆だからこその木の魅力もあります。
また、落合さんの作品で、器の表面をノミで削っていくものが少なくありません。
つるんとしたものもよいですが、ノミ目の柔らかな凹凸が手にしっくりときます。
造形もゴテゴテしたものではなく、すっきりモダン。和にも洋にも料理が映えます。
今回、多くのアイテムの漆器を展開します。
漆は決して扱いづらいものではありません。ふだん使いの器として愛着をもって楽しんでいただきたいです。
富田惠子さんの絵のモチーフ
10年以上前だったか、一目ぼれして買い求めた版画が富田惠子さんの作品でした。
昨年初めてお会いした惠子さんは、彼女の年齢よりはるか上の人生の大先輩と話しているような気持になる強い信念を持っている人でした。
大学では史学科を専攻し、考古学、主に北方民族について学んだ。
当時タイミングよく礼文島の調査に関わり、オホーツク文化の手がかりとなる骨角器を採掘していたのだそう。
誰も観ていない太古の昔のことを、出てきたモノに対していろいろなアプローチをし、そこから想像を膨らませることが楽しいとおっしゃいます。
大学卒業後はフリーランスで歴史系雑誌の編集に携わり、それと同時に仕事の後に銅版画工房に通った。
そのうち他誌の編集をするようになり、メモなどにちょこっと描いていた絵がおもしろいと、イラストカットも描くようになりました。
だんだんちゃんと絵を学びたいと思うようになり、絵の専門学校に通いました。
惠子さんの版画は、数ある技法のうちのエッチングで制作されています。
エッチング特有の繊細な線ではなく、ワイルドに描かれた線が魅力です。
昔から四つ足の動物がなんとなく好きで、横から見たそれを絵のモチーフにすることが多い。
その姿から、静けさ、強さ、ゆったり流れる時間が感じられ、それを描くと自分の絵だなぁと思うのだそうです。
半ば抽象的でモノクロの静謐とした表現の中に、たしかに何かがその場に息づいている、不思議とその絵の中に引きこまれるような感覚におちいります。
最近では、平面から立体へと関心が移ってきていて、版画という平面をオブジェを飾るようなイメージで、作品を板状にして質感も追及しています。
ぜひ実物をじっくりと惠子さんの世界観をご覧いただきたいと思います。
コラム vol.87 "関昌生さんの柔軟な発想力 落合芝地さんの拭き漆 富田惠子さんの絵のモチーフ"